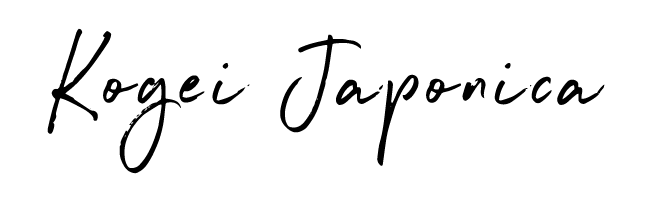富山県高岡市——400年の歴史を誇る鋳物の町に、金属に新たな命を吹き込み続けた一人の偉大な工芸家がいました。2005年に重要無形文化財「鋳金」保持者(人間国宝)に認定された、大澤光民(おおざわ こうみん)氏です。
ドロドロに溶けた約1400度の金属が、土で作られた型へと静かに注ぎ込まれる瞬間。張りつめた空気と、創造への情熱が交錯するその場は、まるで一つの儀式のようでした。漆黒の地金に浮かび上がる赤と白のライン——金属でありながら有機的な温かみすら感じさせるその表現は、どのような過程を経て生まれるのでしょうか。
本記事では、大澤氏の代名詞ともいえる独自技法「鋳ぐるみ」、そして彼が生涯大切に守り続けた伝統技法「焼型鋳造」の全貌に迫りながら、氏の根底に流れる「伝統とは常に新しいものである」という哲学をご紹介します。
なお、大澤光民氏(本名=幸勝〈ゆきまさ〉、鋳金家、人間国宝)は、2023年10月29日、肺炎と心不全のため逝去されました。享年82。ここに謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りいたします。
目次
鋳物の町・高岡が生んだ異端児:職人から芸術家への脱皮と「失敗」から生まれた奇跡
高岡銅器の産地として名高い富山県高岡市。その歴史は慶長14年(1609年)、加賀藩主・前田利長が産業振興のために鋳物師を招いたことに始まります。この地で生まれ育った大澤光民氏は、いかにして人間国宝への道を歩み始めたのでしょうか。
専業農家の長男から「町の鋳物屋さん」へ、そして作家への目覚め
大澤氏はもともと、伝統工芸の家に生まれたわけではありませんでした。高岡市内の専業農家の長男として生を受け、農閑期の仕事として偶然選んだのが、近所の「町の鋳物工場」でした。
20代前半の大澤青年は、そこで置物や胸像などをひたすら作る日々を送ります。しかし、勤続10年が過ぎた頃、彼の中に一つの疑念と渇望が芽生え始めました。「分業の一部を担うのではなく、最初から最後まで自分の手で作りたい」「量産品ではなく、世界に一つだけの作品を生み出したい」。
その思いは彼を突き動かし、11年勤めた工場を退職して独立。ちょうどその頃、高岡市が開設した伝統産業の技術者養成スクールの一期生となり、金工作家の可西泰三氏らから「造形デザイン」や「モノづくりへの心構え」を学びます。それまで「商品」を作っていた職人が、「作品」を生み出す芸術家へと変貌を遂げる転換点でした。
偶然の産物か、天啓か:鉄棒の抜き忘れが導いた「鋳ぐるみ」の原点
大澤氏の最大の功績である「鋳ぐるみ」という技法。実はこの革新的なアイデアの種は、一つの「失敗」から生まれました。
ある日、大澤氏は仏像の鋳造工程で、中型(なかご)を支えるために刺していた「笄(こうがい)」と呼ばれる鉄の棒を抜き忘れたまま、着色工程に出してしまいました。仕上がってきた作品には、当然ながら鉄の棒の断面が丸い跡として残っていました。
通常であれば、それは明らかな「キズ」であり、失敗作として廃棄される運命にあります。しかし、大澤氏の眼にはそれが違って映りました。「この異質な金属の混入を、逆に模様として利用できないか?」。溶けた金属の中に、溶けない別の金属を意図的に配置することで、新しい表現ができるのではないか。この逆転の発想こそが、後の人間国宝・大澤光民を決定づける瞬間だったのです。
3年間の沈黙と探求:日展から伝統工芸への転身
独立後、大澤氏は日展に3年連続で入選するなど、華々しいスタートを切りました。当時の作品は、現代的で抽象的な造形が中心でした。しかし、彼はそこで再び立ち止まります。「造形美」を追求する日展の世界に対し、彼が惹かれていったのは「用と美」、つまり実用性の中に美しさを見出す伝統工芸の世界でした。
彼は日展への出品をやめ、3年間の沈黙期間に入ります。その間、彼は自身の技術を見つめ直し、「自分にしかできない表現とは何か」「日本の伝統工芸として残すべきものは何か」を自問自答し続けました。そして辿り着いたのが、失敗から着想を得た「鋳ぐるみ」の技法と、手間暇を惜しまない「焼型鋳造」への回帰だったのです。この決断が、後の高岡銅器界に新たな風を吹き込むことになります。
独自技法「鋳ぐるみ」の革新性:金属の中に金属を「織り込む」という挑戦
「鋳ぐるみ」とは、鋳型の中にあらかじめ融点の高い別の金属(銅線やステンレス線など)を配置し、そこに溶かした合金を流し込むことで、異なる金属同士を一体化させる技法です。これは単なる象嵌(ぞうがん)のような後加工の装飾ではなく、鋳造のプロセスそのものにデザインを組み込む、極めて難易度の高い技術です。
漆黒のキャンバスに描かれる「光」と「水」の物語
大澤氏の作品の多くは、漆黒に仕上げられた地金の中に、赤く輝く銅線と、白く煌めくステンレス線が走るデザインが特徴です。これには明確なテーマがあります。赤い銅線は「光(陽光)」を、白いステンレス線は「水(月光)」を象徴しているのです。
光と水は生命の源であり、大自然のエネルギーそのもの。大澤氏は、硬質で冷たいはずの金属を用いて、自然界の根源的なテーマを表現しようと試みています。黒い器体は宇宙や大地を表し、そこに走る無数の線は、降り注ぐ光や流れる水を表現しています。
「鋳ぐるみ線文花器」と名付けられた一連の作品群は、見る角度によって金属の光沢が変化し、まるで水面が光を反射して揺らめいているかのような錯覚を与えます。それは、静止した物体でありながら、永遠の「動き」を内包した芸術作品なのです。
計算と偶然の融合:熱が生み出す有機的な「揺らぎ」
「鋳ぐるみ」の真の魅力は、その線が定規で引いたように真っ直ぐではないところにあります。制作工程において、鋳型の中に配置された金属線は、1000度を超える溶湯(溶けた金属)が流し込まれる際の猛烈な熱と圧力にさらされます。
このとき、金属線は熱膨張によって反ったり、ねじれたり、あるいは一部が溶け出したりします。大澤氏は、緻密な設計図を描き、等間隔に釘を打って線を固定しますが、最終的に線がどのような表情を見せるかは、炉から出し、型を割ってみるまで分かりません。
この「熱による自然な変形」が、作品に人工物にはない有機的な温かみと、二度と同じものは作れないという一回性を与えます。計算され尽くした配置と、炎による偶然の作用。この二つが融合することで、大澤光民の作品は完成するのです。
異素材結合の難しさ:数ミリの隙間に込める職人の魂
この技法には、技術的に極めて困難な課題があります。それは、母材となる合金と、埋め込む金属線との「なじみ」の問題です。
溶湯の温度が高すぎれば中の線まで溶けて混ざってしまい、逆に低すぎれば線と母材が癒着せず、隙間ができて作品になりません。また、ステンレスと銅では熱伝導率も膨張率も異なります。これらを同時に鋳込み、冷え固まる過程で割れや歪みが生じないようにコントロールするには、長年の経験と勘、そして卓越した温度管理技術が必要です。
大澤氏は、鋳型の中のわずか数ミリの隙間に、溶けた金属がどのように流れ、どのように線を包み込むかを、目に見えない中でイメージし続けます。その想像力と集中力こそが、人間国宝の技の真髄と言えるでしょう。
伝統技法「焼型鋳造」への回帰と継承:手作業が生み出す唯一無二の肌合い
大澤氏が人間国宝に認定された理由は、革新的な「鋳ぐるみ」の開発だけではありません。もう一つの大きな理由は、効率化の波に押されて消えつつあった伝統的な「焼型鋳造(やきがたちゅうぞう)」という技法を頑なに守り、高度に体現している点にあります。
効率化に背を向けて:なぜ「焼型」でなければならないのか
高度経済成長期以降、鋳物の世界でも生産性が重視され、ガスを使って短時間で硬化させる「ガス型」や「生型」が主流となりました。しかし、大澤氏はあえて、非常に手間と時間がかかる「焼型鋳造」を選び続けました。独立当初、問屋からは「そんな手間のかかることはやめて、安く早く作れ」と言われたこともあったといいます。
それでも彼が焼型にこだわった理由。それは、焼型でしか出せない「肌合い」と「通気性」にあります。土と和紙、そして藁(わら)を混ぜた素材を高温で焼き締めるこの技法は、鋳型自体が高い通気性を持ちます。これにより、鋳造時に発生するガスが綺麗に抜け、鋳肌(いのはだ)にピンホール(気泡による穴)ができにくく、金属の密度が高い、しっとりとした美しい表面が得られるのです。
土と紙と藁の錬金術:「紙土(かみつち)」と「粗土(あらつち)」
焼型作りの工程は、まさに土との対話です。大澤氏が使うのは、「紙土」と呼ばれる特殊な土です。これは、粘土を液状にした「植汁(はじる)」の中に、繊維をほぐした和紙と数種類の土を混ぜ込んで作られます。
1400度の金属が流し込まれた瞬間、土に含まれていた和紙の繊維は一瞬で燃え尽きます。すると、そこにはミクロ単位の無数の空洞が生まれます。これがガスの逃げ道となり、完璧な鋳造を可能にするのです。
さらに、その外側には「粗土」と呼ばれる、藁を混ぜた荒い土を被せます。これも同様に、通気性を確保し、型が爆発するのを防ぐ役割を果たします。先人たちが編み出した、電気も機械もない時代の知恵。大澤氏はその一つ一つの工程に敬意を払い、自らの手で土を練り、型を造形していきます。
10時間の焼成と一瞬の勝負:1400度の溶湯との対峙
型作りが終わると、いよいよ「焼成」です。鋳型を窯に入れ、約10時間をかけて900度まで温度を上げていきます。この工程で型の中の水分を完全に飛ばさなければ、注湯の瞬間に水蒸気爆発を起こし、全てが台無しになります。大澤氏は2時間おきに窯の様子を確認し、長年の経験で焼き上がりを判断します。
そしてクライマックスの「鋳込み」。溶解炉の温度は1400度。真夏には作業場の室温が50度近くにもなる灼熱地獄の中、防護服に身を包んだ大澤氏は、坩堝(るつぼ)から汲み出した輝く液体を、慎重かつ大胆に鋳型へと注ぎ込みます。
「湯を流し込んで、明日型を割るまで結果は分からない。だから緊張するし、やりがいがある」。そう語る大澤氏の表情には、職人の厳しさと少年のようなどきどきが同居しています。翌日、冷えた型をハンマーで割り、中から作品が姿を現す瞬間。イメージ通りの「鋳ぐるみ」が現れたとき、数ヶ月に及ぶ苦労が報われるのです。
まとめ:伝統とは、守るものではなく「創る」もの
大澤光民氏の工房には、今日も土を叩く音と、炉の轟音が響いています。「伝統工芸というと、古いものというイメージがあるかもしれません。しかし、今の時代に合った考え方や感性を取り入れていくことこそが、本当の『伝統』なのです」。
先人の技術への深い尊敬と、そこに安住しない革新への意欲。焼型鋳造という古典的な技法を土台にしつつ、鋳ぐるみという現代的な表現を乗せるそのスタイルは、まさに「温故知新」を体現しています。
光と水、赤と白、土と金属。相反する要素を一つの器の中に調和させる大澤氏の作品は、私たちに「調和」の美しさを教えてくれます。富山県高岡の地で、一人の人間国宝が灯し続ける情熱の火は、次世代の工芸家たちにとっての道標となり、これからも新たな「伝統」を焼き固めていくことでしょう。