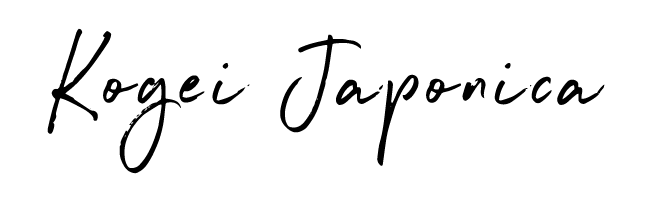村山明(むらやま・あきら、1944年3月25日生)は、欅(ケヤキ)の木を「彫刻素材」として再解釈し、立体造形の地平を大きく広げた現代木工芸家として高く評価されています。刳り物(くりもの)や拭漆といった伝統的技法を基点にしながら、削る・磨く・空洞を計算するといった彫刻的アプローチを融合させ、木を内部から緊張させるような造形を生み出す点が特徴です。
国内外の展覧会で存在感を示し、国際的な木工芸シーンでも「Wood Sculpture」の可能性を提示する作家として注目されています。1989年にはロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館に「欅拭漆盤」が収蔵され、2003年には重要無形文化財「木工芸」保持者(人間国宝)に認定されました。
本記事では、造形思想、技法構造、主要作品の読み解き方から世界的評価まで、村山作品を深く理解するための総合ガイドとして詳しく解説します。
目次
村山 明とは?現代木工芸を牽引する造形作家の全体像
村山明氏(1944年3月25日生)は、京都を拠点に活動する現代木工芸家の中でも、造形的アプローチと素材研究の深さで高い評価を得てきた作家です。
ノミやカンナを使った刳り物(くりもの)・拭漆といった木工芸の基礎技法に加え、欅(ケヤキ)の木質を生かした立体構成、複数の道具を組み合わせた加工技術など、多段階のプロセスを組み合わせることで独自の造形語彙を築き上げています。本章では、略歴、作風変遷、評価のポイントを整理し、村山氏の全体像を立体的に紹介します。
略歴と活動領域:京都を拠点とした木工芸の主要作家
村山明氏は、木工芸の伝統と現代性が共存する京都を拠点に活動してきました。京都の工芸文化は、器形の美学から素材研究、加工技術まで多様な系譜が重なり合うため、村山氏が追求する「木を素材とした刳り物造形」に強い影響を与えています。
氏は1966年の黒田辰秋への師事から、刳り物・拭漆といった基礎技法を徹底的に習得し、その後、実用的な器の領域を超えた立体造形表現へと活動領域を広げました。作品は国立美術館での収蔵をはじめ、ヴィクトリア&アルバート美術館(ロンドン)など国内外の重要施設に収蔵される例が多くあります。
2003年に重要無形文化財「木工芸」保持者(人間国宝)に認定され、日本工芸会参与・京都工芸美術作家協会副理事長として、後進への技術継承と工芸の新たな表現方法の提示に携わっています。こうした幅広い活動は、京都の工芸環境が持つ「開かれた創造性」と強くリンク]し、村山氏を現代木工芸の主要作家へと位置づけています。
初期作から現在までの作風変遷:刳り物・拭漆の深化
村山氏の作風は、黒田辰秋への師事以降、ノミやカンナを使った「刳り物(くりもの)」に特化してきました。初期は欅(ケヤキ)の木質を活かした器形作品から始まり、木目の方向性と木の可塑性を丁寧に読み取る姿勢が見られます。
中期以降、氏は単なる実用的な器の枠を越え、木を「立体素材」として扱う方向へシフトしました。異なる厚さの木板を重ね合わせる、乾燥段階での木の動きを予測し形を構成する、内部の空洞を計算して張りを持たせるなど、素材の性質を造形言語として取り込むスタイルが確立します。
現在では、曲線と量塊を両立させる抽象的フォルムや、木の経年変化を意図的に受け入れる作品も多く、拭漆仕上げによる光沢と木地の質感が共存した独自の世界観が特徴です。この変遷は、伝統工芸の枠を越える姿勢の表れといえるでしょう。
国内外の展示・受賞歴が示す評価と影響力
村山氏は、国内の工芸系ギャラリーだけでなく、現代美術系のスペースでも注目されてきました。1987年には東京国立近代美術館の「木工芸 明治から現代まで」に招待出品され、1989年にはロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館に「欅拭漆盤」が収蔵されました。京都・東京を中心とした個展や企画展に加え、国内外のギャラリーが取り扱うケースも増えており、器物から立体造形まで幅広い形式の作品が紹介されています。
受賞歴には日本伝統工芸展での朝日新聞社賞(1970年)や日本伝統工芸近畿賞(1992年)をはじめ、京都府文化賞功労賞(2004年)、紫綬褒章(2005年)、旭日小綬章(2014年)、京都市芸術文化協会賞(2018年)など、工芸・文化全般を対象とする公的表彰が含まれています。
特に「木を素材とした立体造形」における木工芸の可能性を広げた点が高く評価されており、欅を主材として拭漆仕上げで実現した独特の造形表現は、国内外の若手作家に影響を与え、現代木工芸の潮流のひとつとして認識されています。2003年の重要無形文化財「木工芸」保持者(人間国宝)認定、および日本工芸会参与・京都工芸美術作家協会副理事長といった職責は、村山氏が単なる職人に留まらず、素材研究者・造形作家として国際的評価を得る存在であることを示しています。
造形思想と美学──「形」を超えて空間を作る木工芸
村山明氏の作品世界を読み解くためには、単に「ノミやカンナで木をくり抜く」という木工芸の技術にとどまらず、完成した造形が空間とどう関係し合うかという視点が欠かせません。氏は欅の木塊を刳り物の手法で操作しながら、表面に現れる曲線や光沢、内部の空洞を使って「重力感」や「静寂」を生み出そうとします。つまり、完成した作品そのものよりも、それが置かれた空間全体との緊張関係を含めて、一つの造形として成立させようとしているのです。
Art Powers Japanの解説によれば、「とてもシンプルな作品に見えるのだが、よく見ると思いもかけない仕掛けが浮かび上がり、だんだんと、単純な構造ではないとわかってくる。平らで直線的な面だと思ったら、機能の反りのふくらみとふくらみが重なり合っていたり、柔らかなふくらみが隠されていたりする」と述べられています。本章では、フォルム、表面質感(拭漆による艶)、空間性の三つの軸から、村山氏が木工芸に見出した彫刻的アプローチと美学を整理します。
フォルムの特徴:曲面・陰影・木目による彫刻的アプローチ
村山氏のフォルムには、ノミやカンナで木を「削り・くり抜く」という刳り物の操作が多層的に組み込まれています。特に特徴的なのが、作品表面に現れる曲面の構造で、これは欅の木質を見極めながら、削り出す工程によって生まれるものです。曲面が生むリズムは、木の年輪を思わせるテクスチャーとなり、表面の凹凸が陰影を複雑に変化させます。
また、曲面の扱いも巧みで、木の可塑性を極限まで引き出しながら、柔らかさと張りのバランスを保ちつつ量塊を支える形態を生み出しています。YouTubeで公開されている映像では、「設計図はなく、鉛筆で大まかな目印をつけるとあとは感覚を頼りに削っていく」と述べられており、村山氏は「重みを持ちながら浮遊感のある形」を理想形のひとつとして追求しているように見えます。拭漆による光沢によって輪郭が溶け込むように見える作品も多く存在します。
こうしたフォルムの扱い方は、木工芸と彫刻の境界を曖昧にし、木という素材の内側に潜む動きを可視化する表現へつながっています。
表面質感の追求:削り・拭漆による質感の深化
村山氏の作品では、表面の質感が造形思想を象徴する重要な要素となっています。ノミやカンナで木を削り出す段階で作られる曲面、木の年輪が浮かぶテクスチャー、削りに応じて現れる木目が複雑に絡み合い、多層的な質感をつくり出します。氏は表面を過度に整えず、欅が持つ粗さ・木目の動き・素材としての重量感を組み合わせることで、触覚的な魅力を引き出しています。
さらに、拭漆の工程によって光沢と質感が大きく変化し、マットな木の表情と光沢のある面を一つの作品の中で共存させることが特徴です。「拭き漆」とは、木地に生漆を塗っては布で拭き取る作業を繰り返すことで、木目を生かしながら美しい艶を生む技法であり、この反復によって木の内部に深みが生まれます。
こうした工程の積み重ねによって、作品は単なる表面装飾を超え、「時間の蓄積が刻まれた肌理」として存在します。観る人は表面の複層構造を通じて、作品に内包された木の個性や素材の記憶を感じ取ることができるのです。
空間との関係性:器からオブジェへ広がる造形的視点
村山氏の作品には、空間との関係性を重視する彫刻的発想が強く表れています。器であってもオブジェであっても、作品の「内側」と「外側」の空間がどう関係するか、置かれた空間にどのような緊張や静けさを与えるかが重要なテーマとなっています。
村山氏自身の言葉によれば、「立体的な形態とは何かを工芸作品の中に表したい」と述べており、これは単なる実用的な器の製作を超えた、純粋な造形表現を目指すものです。内部の空洞を計算したフォルムは、重力のかかり方や作品全体の重心に影響し、立体としての安定感と存在感を生み出します。
また、展示空間に応じて作品が光を受ける角度や影を落とす方向を意識し、視覚だけでなく空間そのものを構成する要素として作品を位置づけています。近年では、器の概念を超えた立体作品が増え、環境や空間全体を作品の一部と捉える傾向が強まっています。
これは木工芸を「造形の場」として捉え直す姿勢であり、村山氏の作品が国内外で彫刻的工芸として評価される理由のひとつといえるでしょう。
技法的分析と制作プロセス
村山明氏の作品を技法面から読み解くと、素材選択から刳り物、乾燥、拭漆に至るまで、あらゆる段階で「欅の木質を読み、その個性を引き出しながらも尊重する」という姿勢が一貫して見られます。氏は、欅の硬度・木目の動き・乾燥時の変化といった木材固有の「振る舞い」を、作品の一部として積極的に取り込みます。
制作プロセスは、欅材の選定から始まり、鉛筆で大まかな目印をつけた後、ノミやカンナで手作業で木をくり抜いていく刳物(くりもの)技法を用いながら、全体の量感と張りのバランスを構築する過程を経ます。最終段階では、生漆を塗っては布で拭き取る作業を繰り返す「拭漆」で表情が決定されます。
本章では、素材選択へのアプローチ、刳り物の技法と手法、拭漆仕上げの三つの側面から、村山氏の作品がどのように立ち上がるのかを詳しく考察します。
素材選択と木地の扱い:欅の特性と向き合う対話
村山氏の制作は、まず「どの欅(ケヤキ)を使うか」という素材選択から始まります。欅は硬度が高く、木目が複雑に動く素材であり、そうした個性が強い木材を削った時にどのような表情が現れるかは、木の性質を読み分けることで決まります。氏は作品ごとに欅の木質を見極め、その動きに応じて削り出す方向や力加減を微調整することもあります。
乾燥段階では、木が収縮するタイミングを見極めながら工程を進めることが重要です。特に、厚みの異なる部分が同時に乾こうとすると歪みやひびが生まれやすく、意図しない破損につながります。しかし氏は、この「乾燥による自然な変化」をあえて作品に取り込むこともあり、素材が示す小さな変化を造形的な魅力として受容します。
つまり「素材を支配する」のではなく「素材と対話する」姿勢で臨むことで、欅という素材の生命感が作品に宿るのです。
成形技法:刳り物・削り出し・内部空間を読む制作法
村山氏の成形技法は、器形を超えた立体造形を実現するために非常に独特です。多くの作品は単一の欅の木塊から、ノミやカンナで内部をくり抜く「刳物(くりもの)」技法によって構築されます。木が湿った段階では、重力によってわずかに沈もうとする力が働き、乾燥が進めば逆に収縮によって外側へ緊張が走ります。氏はその「内側からの力」を読むことで、曲面が自然に立ち上がるような造形を実現しています。
また、ノミで掘る、カンナで削る、手指で押し広げるなど、様々な道具と身体性を組み合わせることで、強い量感と軽やかな曲線が共存するフォルムが生まれます。文化遺産オンラインの記録によれば「木材を手作業で彫ったり削ったりする刳物技法により、欅の木目の美しさを活かした作品」が制作されています。これらの操作は、木工芸の伝統技法でありながら、彫刻的な身体性が求められる作業であり、氏の作品が「木の彫刻」と呼ばれる理由のひとつにもなっています。
拭漆の工程:層の積み重ね・透明感・深みがもたらす最終表情
拭漆は、作品の最終的な光沢・質感・緊張感を決定する極めて重要な工程です。村山氏は、生漆を塗っては布で拭き取る作業を何度も繰り返しながら、作品に最適な深さを探ります。拭漆を重ねることで、漆の透明感が層状に蓄積され、木地が奥行きを伴って見え、マットで柔らかな印象から光沢のある表情へと移行します。
また、拭漆の工程では塗る面積や拭き方によって表面に微妙な光沢の差が出ます。氏はこうした「拭き方による微妙な違い」を積極的に受け入れ、あえて均一な艶を求めません。拭漆を重ねるたびに、手作業では生み出せない自然な艶の深まりが加わることで、最終的に独自の存在感を持つ立体へと仕上がります。
拭漆を「仕上げ」ではなく「対話」と捉える村山氏の姿勢が、作品の奥深い表情につながっているのです。
代表作にみる造形哲学
村山明氏の代表作を読み解くことは、氏が木という素材に託す思想の輪郭をつかむ最良の手段です。作品群には、抽象形態を通じて「動き」や「緊張」を可視化するシリーズと、器物の構造を借りながら彫刻的量塊へ変換するシリーズがあり、いずれも欅が本来持つ硬度・木目の複雑さ・乾燥時の変化といった物質性を深く読み取ったうえで構築されています。
特に代表作である「欅拭漆盤」(1989年、ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館収蔵)は、輪花形の意匠を基本に、村山が工夫した稜線を加え、内と外の二つの世界を結ぶ上縁へ向かって伸びる稜線が広がりを生み出す作品として知られています。また、表面に現れる光の揺らぎや、拭漆による層による視覚的な深さは、木工芸であることを忘れさせる存在感を生み出します。
本章では、代表シリーズを手掛かりに、村山氏の造形哲学そのものを掘り下げます。
抽象形態による「動き」の表現
村山氏の代表的シリーズには、欅の硬度と木目の流麗さを同時に感じさせる「動く形」があります。これは、欅の木塊からノミやカンナで削り出し、木の性質に応じてわずかな曲線の変化を誘発させ、その後に拭漆を重ねることで生まれる独特のシルエットです。表面には木目の筋が走り、それが光を受けて時間的な揺らぎを生み出します。
こうした造形は、動きを直接表すのではなく、木の「痕跡」を彫刻的に残すアプローチといえます。重力がどの方向に働き、木目がどのように動き、乾燥でどう変化したかが造形に刻まれ、作品は「木が存在してきた時間の記憶」として成立します。氏は木の自律的な動きを無視するのではなく、むしろ形に定着させることで、抽象形態でありながら生命的なエネルギーをまとった作品を生み出しているのです。
YouTubeの映像では、「設計図はなく、鉛筆で大まかな目印をつけるとあとは感覚を頼りに削っていく」と述べられており、その「神業」とも言える削り技が代表シリーズを生み出しています。
器物的構造と彫刻性の境界に立つ作品群
もう一つの重要な系列は、器物の構造を借りながら、彫刻作品へと境界を越えるシリーズです。輪華形(りんかがた)や盤形といった「器の形式」を連想させる形は残しつつ、それらを均整に整えるのではなく、あえて張りや傾きを生じさせることで、量塊としての存在感を強めています。
内部の空洞は器物由来の構造ですが、その空洞をどう削り出し、どの方向に木の力を逃がすかで、外形の緊張や膨らみ方が変わります。村山氏はこの「内側の木理(もくり)」を読みながら造形を進めるため、作品には器の機能性とは別次元の造形論理が宿ります。
表面の削り跡や木目の表情は、器としての整いを崩すのではなく、むしろ存在そのものの必然性を強調する役割を果たします。代表作「欅拭漆輪華盛器」も、器としての基本形式を保ちながら、圧倒的な立体性と彫刻的緊張感を備えた作品として知られています。
器の形式を借りながら彫刻的意味へ向かうこのシリーズは、村山氏の思想を象徴する境界的作品群といえるでしょう。
素材を超える視覚効果:木工芸とは思えない質感・量塊表現
村山氏の作品には、木工芸でありながら木工芸に見えない質感を生む特徴があります。削り跡が自然の岩肌のように見えたり、滑らかな曲面が石や金属の質感を思わせたりと、素材の既成イメージを超える視覚的効果が生まれます。
これは、ノミやカンナで削り・押し・磨くといった複数工程で現れる「手仕事による微妙な起伏」をあえて残す手法と、光の反射を計算した曲面設計の組み合わせによるものです。さらに、拭漆による艶が表面に緊張を生み、量塊の輪郭がわずかに立ち上がることで、木工芸とは思えない重厚さや軽やかさが同居する独自の印象をつくり出します。
Art Powers Japanの解説では、「とてもシンプルな作品に見えるのだが、よく見ると思いもかけない仕掛けが浮かび上がり、だんだんと単純な構造ではないとわかってくる」と述べられています。観る者は作品をひと目見て「木の彫刻」という言葉では足りない多義性を感じ取り、素材を超えた造形の可能性そのものに触れることになります。
村山氏の作品が国際的に評価される理由も、この「素材の越境」にあります。
まとめ
村山明氏の作品世界は、木という素材がもつ自然な動き・乾燥時の変化・質感を徹底的に読み取り、その内側に潜む力を造形として可視化する姿勢に貫かれています。器物の構造を参照しつつも抽象的量塊へと変換する代表作は、現代木工芸と彫刻の境界を大きく押し広げ、ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館をはじめ、国内外の美術館・ギャラリーで高い評価を獲得しています。
また、同時代作家との比較においても、素材の生命性を保ちながら造形言語を拡張するアプローチは独自性が際立ち、国際的な「コレクタブル・デザイン」との接続を強める重要な要素となっています。村山氏の活動は、木工芸がもつ可能性を再定義し、工芸・アート・デザインの領域を横断する現代木工芸の新たな基準点として位置づけられています。