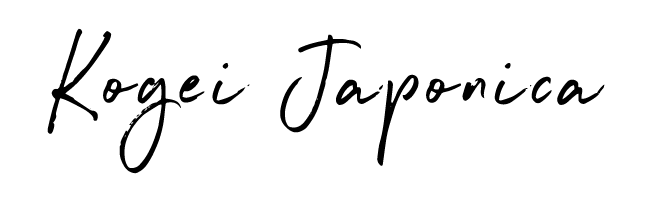目次
異分野が交差する地点で始まった対話
岡山で半世紀以上にわたり縫製文化を支えてきた株式会社さえら 代表取締役社長 木谷実氏と、日本の職人・アーティストと新たなプロダクトを共創してきた株式会社EBRU 代表取締役 佐藤怜氏。
この両社が出会ったのは偶然ではなく、「ものづくりの本質を問い直す」という必然の中で実現した対話でした。
工芸ジャポニカ編集長の佐藤誠一氏も同席し、議論に参加しました。
対談では技術の継承、人材・教育、デザインの役割、プロダクトの寿命、医療領域への拡張可能性など、多岐にわたるテーマが掘り下げられました。
会社紹介:それぞれの歩みと理念
さえら — “まとうことの美学”を追求する手仕事の系譜

株式会社さえらは 1974 年に創業し、ナイトウェアやランジェリーを中心とした婦人服メーカーとして歩んできました。
筆染めやレース、装飾モチーフなどの 日本的な手仕事技術を主軸とし、「洋服を作品として届ける」という独自の哲学を守り続けています。
木谷実氏:
「創業以来、一度もセールをしませんでした。安売りされるものではなく、長く愛していただく作品でありたいからです。」
国内一貫生産体制を維持し、時間をかけた少量生産によって唯一無二の風合いと技術を宿らせています。
EBRU — 「アート × 職人 × 音」で新しい表現を生むブランド
株式会社EBRUは、伝統素材や技法、そして職人との共創を通じて、ファッション、ジュエリー、音響デバイスなどを制作する企業です。
代表作「EARMIND」は、漆やマーブリング技法等で イヤホンを工芸作品へ昇華するブランドです。
佐藤怜氏:
「ファッションと工芸は別物ではなく、日本のものづくりを支える大きな文化体系だと思っています。」
アート作品を身につけることで、日常に美意識を宿し、作り手とユーザーの精神的な距離を縮めようと試みています。
出会いの背景 — 展示という“共感の入口”

対談のきっかけは、木谷氏が松屋銀座での EBRU の展示を目にしたことでした。
木谷実氏:
「工芸がファッションやアートとして昇華されているのを感じ、職人の活用方法に深く感銘を受けました。」
熟練した縫製人材の減少、技術継承の難しさ、地域ものづくりの疲弊——両社は共通課題に気づき、この対話が生まれました。
ものづくりの核心 — 技術、対話、そして精神性
さえらが守り続ける“一点の精神性”

デザイン〜裁断〜縫製まで全て社内で完結する稀有な体制を持つさえら。
この構造が 職人との対話の密度を極限まで高めてきました。
木谷実氏:
「デザイナーが自分で縫うからこそ、意図が伝わりますし、最終的な質も保てるんです。」
同社はアート的な衣服として商品を捉え、長く所有してもらう哲学を掲げます。
EBRUが提示する “装着する工芸”

EARMIND の開発は、イヤホンを文化財のように扱う挑戦でした。
佐藤怜氏:
「内部構造を考えつつ、耳の外に見える表情がどうあるべきか考え続けました。」
同ブランドのPVは金沢の舞踏家や美大出身のアーティストが参加し、音楽まで手作りされました。
これは単なる製品紹介ではなく 文化コンテンツとしての発信だったといえます。
技術と対話 — 世代と領域を超える創造
デザイナーと職人が同じ場所で議論し、壁を乗り越えていく重要性について、両者の認識は完全に一致していました。
佐藤怜氏:
「現場で対話することで心が開き、同じ目線になれるんです。」
木谷実氏:
「エブルさんの取り組みは職人に新しい道筋を示しています。」
社会課題としての“職人不足”と教育の問題
両社の対談で最も熱を帯びたテーマは ものづくり教育の機会の創出、推進でした。
木谷氏は岡山でワークショップや授業を行い、教育現場と向き合っています。
木谷実氏:
「子どもたちがレースに触れるだけで目が輝きます。本当に触れる機会が減っています。」
佐藤怜氏も幼児〜中高生を対象に色や素材の体験授業を実施しています。

「興味は出会いの中で育つんです。そこに環境が必要なんですよ。」
日本では技術職の人材不足や継承の停滞が進む中、この領域は今後さらに重要性を増す話題です。
議論から浮かぶ“新しい未来像”
対談の深まりとともに、複数の未来可能性が語られました。
補聴器など医療機器領域への応用
木谷実氏:
「眼鏡がデザインで変わったように、補聴器も変えられるではないかと可能性を感じています。」
佐藤怜氏:
「私たちも以前に挑戦したことがありますが、医療認可の壁が高く、参入には長い時間と資本が必要なのです。」
リペア・リメイクという文化資産への発展
佐藤怜氏は、壊れても直して使いたいと感じるモノが持つ価値を語りました。
木谷氏も賛同し、さえらの衣服が 子どものベビードレスからウェディングドレスへリメイクされた事例を紹介しました。
「製品が人生に寄り添っている」と強調します。
ものづくりの物語
工芸ジャポニカ編集長・佐藤誠一氏がこうしたリアルな対談を広く世に伝える重要性を述べました。
佐藤誠一氏:
「今日の対話で語られた背景や思想そのものが、製品の価値を深める重要なコンテンツになると感じています。物語を届けることで、使い手は意味や背景に触れ、製品への理解と愛着がより豊かに広がっていきます。」
直面する現実 — ハードルもまた創造の源泉
量産との乖離、医療領域の参入障壁、職人との対話の複雑さ——
これらの課題は、同時に“文化を変える挑戦の入り口”でもあります。
さえらは、半世紀以上、量産を拒んできました。
EBRUは、アート的試みを市場に持ち込み続けています。
両社の姿は、課題解決ではなく「文化創造」として挑戦し続ける象徴です。
結び:ものづくりの未来は“対話”がつくる
今回の対談は、単に企業同士の意見交換ではありませんでした。
価値観の共有であり、文化をつくるための対話そのものでした。
私たちが衣服やアクセサリー、イヤホンを見るとき、
そこには “機能” 以上に、
- 作り手の人生
- 美意識
- 技術
- 物語
が宿っています。
株式会社さえらと株式会社EBRUが描く未来は、技術・教育・文化の再定義です。
その動きがどのような形をとって世の中に現れるのか——
工芸ジャポニカとして今後も追い続けていきます。