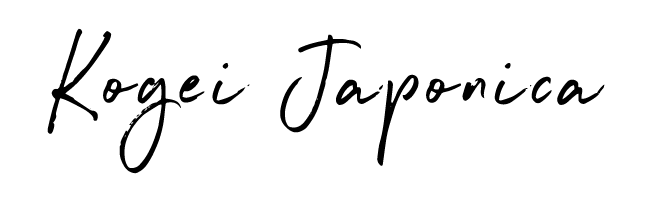松本家具(まつもとかぐ)は、長野県松本市を中心に発展してきた日本有数の家具産地です。木の質感を活かした温もりあるデザインと、熟練職人による確かな技術で知られ、全国の家具ファンから高い評価を得ています。
伝統的な木工技術と現代的なデザイン感覚を融合させた家具づくりは、国内のみならず海外でも注目を集めています。
この記事では、松本家具の歴史や特徴、代表的な工房、そして長く愛され続ける魅力について詳しく解説します。
目次
松本家具とは?──木工の街・長野県松本が育んだ匠の家具文化
松本家具とは、長野県松本市を中心に発展した日本有数の木工家具ブランドであり、手仕事の温もりと実用美を兼ね備えた家具として知られています。松本は古くから城下町として栄え、周囲の山々から得られる豊富な木材資源を背景に木工文化が発展しました。
戦後は「松本民芸家具」の名で全国的に知られるようになり、無垢材を用いた堅牢で美しい家具づくりが受け継がれています。その特徴は、単なる量産品ではなく、使い手の暮らしに寄り添い、長年使うほどに味わいが増す「生きる家具」。松本家具は今も日本のクラフト精神を体現する存在として高く評価されています。
松本家具の起源と歴史──城下町から発展した木工の系譜
松本家具の起源は、安土桃山時代末期(16世紀後半)の松本城築城とともに城下町が形成された時期にまで遡ります。 松本市周辺では、豊富な木材と乾燥した気候という家具作りに適した環境の下で、木工や指物(さしもの)職人が多く住み、箪笥や箱物、建具などの製作を手掛けていました。
江戸時代中期(18世紀)になると、庶民の間でも家具への需要が拡大し、松本家具は地域産業として本格的に発展します。 大正末期(1920年代)には日本一の和家具の産地として繁栄し、全国屈指の生産高を誇るまでになりました。
しかし、太平洋戦争後の社会変化により松本家具は急激に衰退し、産業存続の危機に直面します。 この時期に衰退を憂いた民芸運動の提唱者・柳宗悦の強い勧めにより、昭和23年(1948年)、池田三四郎が松本民芸家具の製作を開始したことが現在につながる松本家具復興の出発点となりました。
池田三四郎は柳宗悦の紹介で安川慶一(初代富山民芸館館長)を指導者として迎え、戦後の混乱で無職となっていた松本の木工家具職人たちに洋家具づくりを要請しました。 この時期から柳宗悦が毎夏松本を訪れるようになり、濱田庄司、河井寛次郎、バーナード・リーチなど民芸運動の錚々たる顔ぶれが松本を訪れ、松本民芸家具の製作指導に協力して基礎が築かれました。
確立されたデザイン哲学と技術体系が現在の松本家具ブランドの礎となっており、昭和50年(1975年)には経済産業省(当時の通商産業省)により「伝統的工芸品」に指定されました。 伝統と生活デザインが融合した松本家具は、地方発クラフト産業の成功例として評価されています。
木の美しさを生かすデザイン哲学──機能と意匠の調和
松本家具のデザイン哲学は、「素材を生かす」ことにあります。ミズメザクラ(水目桜)主要材をはじめとする国産の無垢の木材が持つ自然な木目や質感を最大限に引き出し、過剰な装飾を排した端正な造形が特徴です。
職人たちは、木の種類や乾燥具合を見極めながら、最適な加工法を選び、一つひとつ丁寧に手仕上げを行います。
さらに、強度と美観を両立するために伝統的な「ほぞ組」や「蟻組」といった接合技術を活用し、「違胴付留ホゾ差鯱栓接(ちがいどうつきとめほぞさししゃちせんつぎ)」、通称「鯱(しゃち)留」など、松本家具特有の複雑で精密な組接技法が用いられています。
釘や金具に頼らずとも堅牢な構造を実現します。 このようにして生まれる家具は、シンプルながら温もりに満ち、長年使い続けても歪まず、分解・再組み立てによる修理が可能で、受け継がれる耐久性を持ちます。
「通常のラッカー仕上げで8回、漆仕上げになりますと13回以上時間を掛けて丁寧に塗り重ねられ」、使い込むほどに深い味わいを増す仕上がりとなります。機能性と美意識の融合こそ、松本家具が国内外で支持される理由といえるでしょう。
受け継がれる職人技と地域ブランド──「松本民芸家具」への展開
松本家具の名を全国に広めたのが、1948年(昭和23年)に創業者・池田三四郎氏によって民芸家具の製作が開始された「松本民芸家具」です。 池田三四郎氏を中心に、1953年(昭和28年)にバーナード・リーチが来訪し、英国ウィンザーチェアの製作指導を行い、日本の指物技術を融合させた独自のスタイルを確立し、「用の美」を体現する家具として高い評価を受けました。
松本民芸家具は、厳選されたミズメザクラなど主に東北産の国産広葉樹を使用し、全工程を手作業で行う点に特徴があります。 職人が数十年にわたり技を磨き、同一デザインでも微妙に異なる木目や手触りが生まれることが魅力です。
今日では、1972年(昭和47年)に設立された松本家具工芸協同組合を中心として、松本地域の複数の家具工房が協同し、ブランドの品質と理念を守りながら製作を続けています。
松本ホテル花月などの地元ホテルの内装として使用されているほか、国内外での評価も高く、1957年にはロックフェラー三世より受注を受けニューヨークのロックフェラーセンターに椅子数点を納品するなど、海外でも認知されています。伝統を礎に未来へ進む松本家具は、地域工芸の理想形の一つといえるでしょう。
松本家具の特徴と魅力
松本家具の魅力は、手仕事の確かさと素材の誠実さにあります。無垢材の質感を活かした造形と、何十年もの使用に耐える堅牢な構造、そして日本的な静けさをまとったデザインが特徴です。
華美な装飾を排した端正なフォルムは、和室にも洋室にも自然に溶け込み、暮らしの風景を上質に演出します。また、使い込むほどに艶や風合いが増すのも魅力で、修理・再塗装を重ねながら代々受け継がれる家具としての価値を持ちます。
ここでは、素材、構造技法、デザインの3つの側面から、松本家具の特徴を掘り下げていきます。
厳選された国産無垢材──木目と質感が生み出す温もり
松本家具の多くは、ミズメザクラを主要材として、楢(ナラ)、栃(トチ)、欅(ケヤキ)、楓(カエデ)、栓(セン)など国産広葉樹を使用しています。 これらの木材は耐久性と美しい木目に優れ、家具として長期間使用しても歪みや割れが生じにくいのが特徴です。
木材は自然乾燥と人工乾燥を丁寧に組み合わせ、含水率を均一に保ちながら加工されます。
自然乾燥では最低1年、長いものでは5年、10年野積みされた後、人工乾燥で70〜80時間かけて含水率を30%から8〜9%まで低下させ、その後1ヶ月ほどシーズニングを行います。
特にミズメザクラは、松本家具を象徴する素材であり、虎の紋様のような「虎斑(トラフ)」と呼ばれる特徴的な杢目があり、きめ細かい肌理とほのかな赤みが深い落ち着きを与えます。
仕上げにはラッカー塗装(通常のラッカー仕上げで8回、漆仕上げで13回以上塗り重ね)や拭き漆が使われ、ウレタン塗装とは異なり、木の呼吸を妨げずに艶を増していく点も魅力です。自然素材へのこだわりが、使うほどに美しく育つ家具づくりを支えています。
伝統的構造技法による堅牢なつくり──「用の美」を支える職人技
松本家具の堅牢性を支えるのが、指物技術を応用した「ほぞ組」や「蟻組」といった伝統的構造です。
これらは金具に頼らず木と木を噛み合わせて接合する技法で、長年の使用にも耐える強度を実現します。
例えば椅子やテーブルでは、脚と天板の接合部に見えない工夫を施し、力の分散を計算した構造に仕上げます。
また、接着剤の使用を最小限に抑え、木の収縮や膨張に自然に対応する設計がなされている点も特徴です。
こうした伝統技術の蓄積により、松本家具は「直して使う」ことを前提とした長寿命設計を可能にしています。まさに「用の美」の精神を具現化した職人仕事といえるでしょう。
普遍的なデザインと暮らしへの調和──民藝思想の継承
松本家具のデザインは、民藝運動の思想を基盤にしています。実用性を重視しながらも、美的感覚を備えた「用の美」の考え方が形に表れています。
椅子や棚などは直線と曲線のバランスが絶妙で、構造そのものが意匠となる設計です。木の色味や質感を際立たせるため、塗装や装飾は最小限にとどめられ、素材そのものの存在感が空間に静かな力を与えます。
そのため、和室・洋室を問わず調和し、年月を経ても古びず、むしろ深みを増す魅力があります。現代のインテリアにも自然に溶け込むその普遍性こそ、松本家具が「時代を超えて愛される家具」と呼ばれるゆえんです。
松本家具の代表的な工房と人気シリーズ紹介
松本家具の魅力は、地域に根ざした複数の工房がそれぞれの哲学と技術で独自の家具づくりを行っている点にもあります。いずれも「手仕事による量産」を掲げ、木材の個性を最大限に活かしながら、長く使える家具を届けています。
なかでも、「松本民芸家具」「atelier m4」などは、木工家具の工房でも国内外で高い評価を受ける代表的な存在です。
それぞれの工房が受け継ぐ伝統と現代的な感性を融合し、リビングやダイニングなど生活空間に調和する家具シリーズを展開しています。ここでは、松本家具を象徴する2つの代表工房と人気シリーズを紹介します。
松本民芸家具──日本民藝思想を継ぐ老舗ブランド

代表作である「S型ビューロー」やライティングビューローは、無駄のない造形と堅牢な構造で長年愛され続けています。 すべての家具は職人による手仕上げで、仕上げ塗装には拭き漆やラッカー塗装が採用され、使い込むほどに艶と深みが増します。
1936年(昭和11年)に創設された日本民藝館(東京駒場)にコレクションされているほか、松本民藝生活館には松本民芸家具をはじめ国内外の優れた民芸家具が収蔵され、職人の修業の場として使用されています。
1957年にはロックフェラー三世の依頼でニューヨーク・ロックフェラーセンターに椅子数点を納品するなど、日本の木工家具として国際的な評価も高く、松本家具の伝統を象徴するブランドです。
atelier m4──伝統技術と現代感覚をつなぐ木工工房
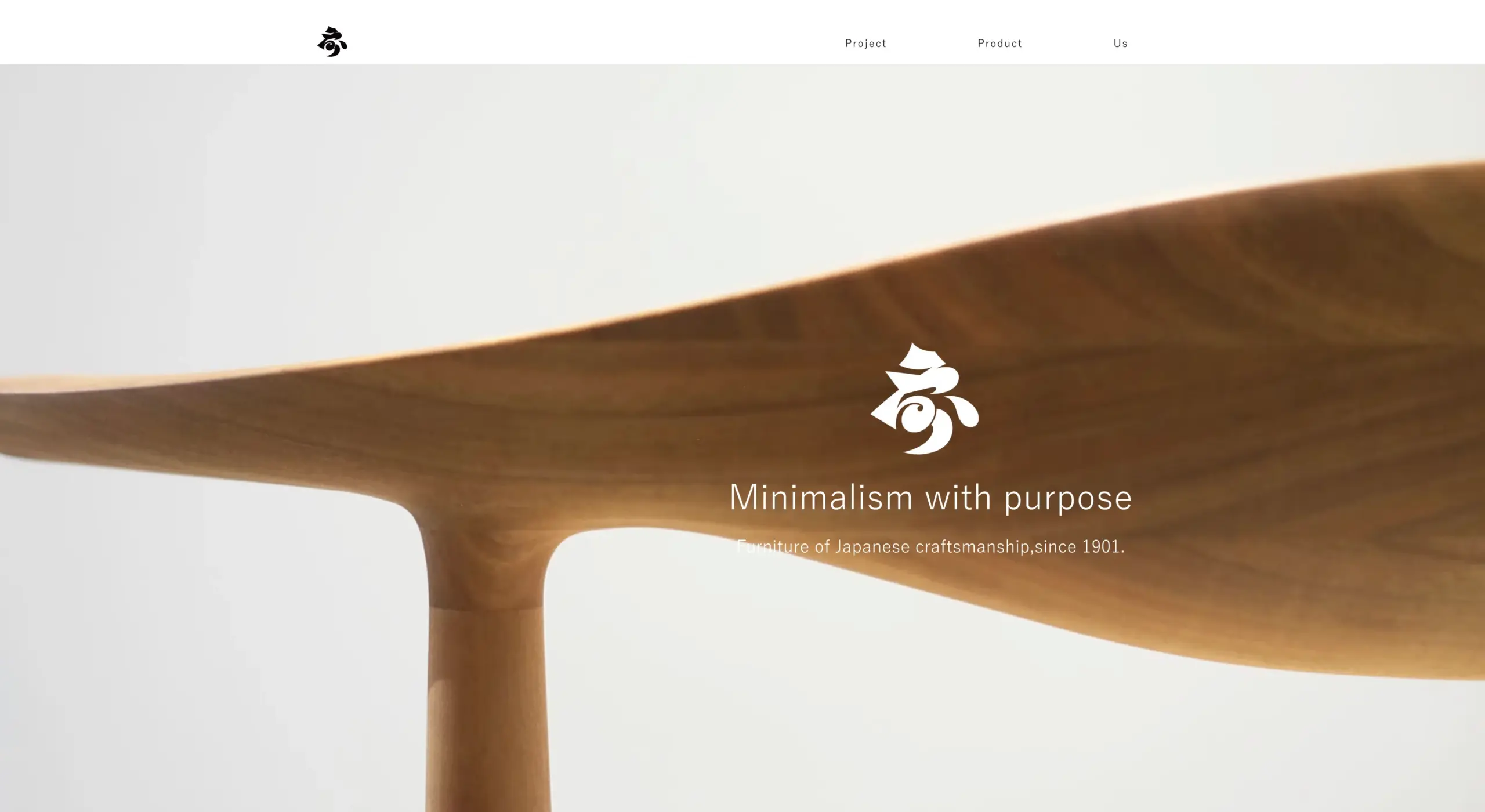
家具全体をひとつの“かたまり”と捉え、接合部の精緻な造形をアクセントにすることで、構造美と素材感を際立たせています。
使用材には信州産カラマツやミズメザクラなど国産広葉樹を厳選し、木取りから組み立て、面取りや仕上げまでをすべて手作業で行うことで、一点一点に職人の息づかいが宿ります。
代表作としては、スツール “Bridge” やダイニングテーブル “Paddle” シリーズがあり、いずれも無駄をそぎ落としたプロポーションの中で木目を際立たせるナチュラルフィニッシュが特徴です。
atelier m4の作品は、松本市内の「m4城東スタジオ」に常設展示されるほか、国内外のデザインイベントやギャラリーにも出展されています。
近年では建築家とのコラボレーションによる住宅プロジェクトや商空間の什器製作も手掛け、伝統的な木工技術と現代の住空間をつなぐ存在として高い評価を得ています。
松本家具の制作工程と職人のこだわり
松本家具の価値は、見た目の美しさだけでなく、一本の木を家具に仕立てるまでの丹念な工程にあります。
大量生産とは異なり、職人が木の状態を見極めながら一脚ずつ手で仕上げるため、同じモデルでも木目や表情が微妙に異なります。
制作の工程は、素材の選定から乾燥、製材、組立、研磨、塗装、仕上げに至るまで十数の段階を経て完成します。そのすべてにおいて、機械と人の手が補い合い、精度と温もりを両立しているのが松本家具の特徴です。ここでは、木材選定から完成に至るまでの職人のこだわりを具体的に見ていきます。
木材選定から完成まで──一脚に込められた手仕事の工程
松本家具づくりは、まず木材選定から始まります。
使う木材は、伐採後に自然乾燥と人工乾燥を組み合わせ、含水率を均一化することで割れや反りを防ぎます。
木目の方向や節の位置、色合いを見極めながら、用途に応じて最も適した部位を選定。これは長年の経験がなければ判断できない工程です。
その後、製材された部材を伝統的なほぞ組などの技法で接合し、構造強度を高めます。
研磨では数種類のヤスリを使い分け、角の取り方ひとつにも神経を使います。
塗装や仕上げは季節によって乾燥時間を調整し、最後に艶出しと検品を経て完成。
1脚の椅子を仕上げるまでに数週間を要することも珍しくありません。
時間と手間を惜しまない工程こそが、松本家具の品質を支えています。
伝統技術と現代機械の融合──精度と温もりを両立
松本家具の工房では、古くからの手道具と最新の木工機械が共存しています。
例えば、精密な穴加工や曲線の切り出しにはCNC(コンピュータ制御)マシンを用い、均一な仕上がりを実現。
一方で、木口や接合部の最終仕上げは必ず職人の手で行い、機械では出せない柔らかな質感を残します。こうした「機械+手仕事」のハイブリッド体制により、効率化と品質の両立を図っています。
また、工房によっては、若手職人が3D設計ソフトを使いながら伝統技術を再構築する試みも進んでおり、クラフトとテクノロジーが融合する新時代の松本家具が生まれつつあります。この柔軟な姿勢が、時代を超えて魅力を保つ理由の一つです。
塗装・仕上げへの美学──拭き漆とオイルが生む深い艶
松本家具の最終工程である塗装・仕上げは、家具の印象を決定づける重要なステップです。
代表的なのが「拭き漆仕上げ」。漆を塗っては拭き取り、薄い層を何度も重ねることで、透明感のある艶を生み出します。
また、オイルフィニッシュでは天然オイルを用い、木の導管を塞がずに保護するため、木目の立体感や手触りの温もりがそのまま残ります。職人は天候や湿度に応じて塗り方を微調整し、数日間かけて自然乾燥させながら仕上げます。
こうして完成した家具は、光の当たり方によって異なる表情を見せ、使い込むほどに深みが増します。塗装の工程にも、使う人への思いや美意識が息づいているのです。
松本家具の現代的価値と海外展開
松本家具は、国内の伝統工芸品としてだけでなく、国際的なデザインシーンにおいても注目を集めています。
北欧家具に通じるミニマルな美しさと、無垢材の温かみが融合しているため、海外のバイヤーやインテリアデザイナーから高い支持を得ています。
また、環境配慮や持続可能性への意識が高まる中で、天然素材を使い、長く使える製品を提供する松本家具の理念は、世界的なトレンドとも一致しています。
ここでは、松本家具の国際的価値を「デザイン性」「サステナビリティ」「市場拡大」の観点から掘り下げます。
北欧デザインとの共鳴──シンプル美がもたらす国際評価
松本家具が海外で高く評価される理由の一つが、そのデザインの普遍性です。過剰な装飾を排したシンプルな造形、素材の質感を重視した構成、実用性と美観を両立する設計思想は、北欧デザインに通じるものがあります。
実際、現在世界的に人気を集める「Japandi」スタイル(日本と北欧の融合インテリア)の文脈で、日本のミニマルデザインが注目されており、松本民芸家具の理念もこの潮流と合致しています。
さらに、国内では建築家やホテルデザイナーがインテリアに採用する例も増えており、伝統工芸の領域を超えたデザインブランドとしての地位を確立しつつあります。松本家具の静かな美は、グローバルな価値観にも響く「普遍のデザイン」なのです。
サステナブルな素材循環と長寿命設計
松本家具の工房では、木材の持続的利用を重視しています。伐採する木を最小限に抑え、端材も小物製作や修理部品として再利用するなど、環境負荷を低減する仕組みが整っています。
さらに、家具自体も「修理しながら長く使う」ことを前提に設計されており、ネジや接合部の構造を工夫することで再塗装やパーツ交換が容易に行えるようになっています。これは大量消費型のインテリア製品とは対照的な発想であり、持続可能なライフスタイルへの関心が高い海外市場でも共感を呼んでいます。
家具が「使い捨て」ではなく「育てる」対象であるという考え方は、松本家具の根幹を支える哲学です。
インバウンド需要と輸出拡大──工芸ブランドとしての成長
これにより、単なる商品販売にとどまらず、「体験型クラフトツーリズム」としての価値が生まれています。さらに、海外展示会やオンライン販売を通じて輸出も拡大。特にアメリカ、北欧、シンガポールなどでの需要が高まっています。
国内では文化財修復や高級宿泊施設のインテリア導入も進み、松本家具は地域工芸の枠を超えた総合的なデザインブランドへと成長を遂げています。
まとめ
松本家具は、長野県松本市に根ざした木工の伝統と、現代のデザイン感覚が融合した日本を代表する家具文化です。無垢材の質感を生かした手仕事、伝統的な構造技法、そして時を重ねるほどに美しさを増す素材の魅力が、多くの人々を惹きつけています。
民藝思想を背景に育まれた「用の美」の精神は、今日ではサステナブルな価値観や国際的なデザイン潮流とも共鳴し、世界の舞台でも高く評価されています。松本家具は、職人技と地域文化の結晶として、これからも暮らしの中に息づく“生きた工芸”であり続けるでしょう。