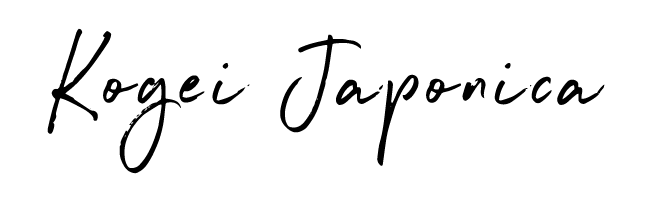「丸亀うちわ」は、香川県丸亀市で生産される日本を代表する伝統工芸品の一つです。竹と和紙を巧みに組み合わせた丈夫なつくりと、美しい意匠が特徴で、全国のうちわ生産量の大部分を占めています。
江戸時代から続く技法は今も受け継がれ、手仕事による繊細な骨組みや塗り、仕上げには職人の高い技術が光ります。
この記事では、丸亀うちわの歴史や特徴、制作工程における職人技、そして現代の暮らしや観光で再注目される魅力について詳しく解説します。
目次
丸亀うちわとは?──四百年の伝統を誇る香川の竹工芸
丸亀うちわは、香川県丸亀市を中心に生産される日本三大うちわのひとつで、竹と和紙が織りなす美しい工芸品です。その起源は江戸時代初期にまでさかのぼり、僧侶が京の都から持ち帰ったうちわ作りを広めたことに始まります。
丸亀は竹の産地であり、城下町として職人文化が発展したことから、精緻な仕上げと実用美を兼ね備えたうちわづくりが根づきました。現在では、国の伝統的工芸品に指定され、全国の祭りや日用品としてはもちろん、海外のデザインフェアでも注目されています。
竹のしなやかさと手仕事の温かみが共存する丸亀うちわは、まさに「使って美しい」工芸の代表格です。
起源と歴史──江戸の信仰から庶民の実用品へ
丸亀うちわの歴史は、約390年前の江戸時代初期にさかのぼります。寛永10年(1633年)に金毘羅大権現の別当金光院住職宥睨(ゆうげん)が、金刀比羅宮参詣の土産物として朱赤に丸金印の渋うちわを考案したのが始まりと伝えられています。
これが次第に評判を呼び、天明年間(1781~1789年)には丸亀藩が下級武士の内職として奨励したこともあり、城下町の商人や職人の手によって産業として発展していきました。江戸後期には丸亀港が金毘羅船の発着で賑わい、参拝客の土産物として全国へ流通し、庶民の日常生活に欠かせない夏の道具となります。
明治以降は観光土産や広告うちわとしても需要が増え、昭和30年代(1955年~1964年)には最盛期を迎えました。現在も年間約1億本を生産し、全国シェアの約90%を占める日本一のうちわ産地として、国内外にその名を知られています。平成9年(1997年)には国の伝統的工芸品に指定され、伝統と産業の両立こそが、丸亀うちわの最大の特徴といえるでしょう。
素材と技法──一本の竹から生まれる繊細な造形
丸亀うちわの魅力は、わずか一本の竹から骨と柄を削り出す製法にあります。現在の主流である「平柄うちわ」では、竹を割り、放射状に広げて骨組みを作る工程は高い技術を要し、職人は竹の節や厚みを見極めながら均一な弾力をもたせて削ります。
その上に和紙や布を貼り、型抜き・乾燥・縁巻きを経て仕上げるまで、47の工程をすべて手作業で行います。
和紙には
- 越前和紙
- 阿波和紙
- 因州和紙
- 土佐和紙
など各地の手漉き和紙が使われ、通気性と強度を両立。
貼り合わせる糊の配合は和紙の厚さに応じて調整され、乾燥時間も職人の経験によって微妙に調整されます。
この一連の手仕事が、軽さと耐久性を兼ね備えた仕上がりを生み、量産品にはない手触りと温もりをもたらしています。一本の竹から約100~200本のうちわが作られ、竹のしなやかさを最大限に引き出す技が、丸亀うちわの真髄です。
意匠とデザインの多様化──伝統を超える現代の表現
丸亀うちわは、単なる日用品から、アート・デザインの分野へと発展を遂げています。伝統的な無地や藍染のほか、絵師による手描きの図柄、友禅染や金箔装飾を施した高級品など、用途や季節に応じた多彩なデザインが生まれています。
近年では、現代アーティストやデザイナーとのコラボレーションも盛んで、透明フィルムや木版画技法を応用したうちわも登場。インテリアやギフトとしても人気を集めています。特に「香川のうちわ職人プロジェクト」では、伝統技法を継承しつつ新しい感性を融合する取り組みが進んでおり、若手職人が国際展示会で発表する機会も増えています。丸亀うちわは、伝統工芸の枠を超え、時代に寄り添うデザインへと進化しているのです。
丸亀うちわの特徴と魅力
丸亀うちわの魅力は、竹の質感、和紙の軽やかさ、そして手仕事による精緻な造形にあります。実用性と美しさを兼ね備えた工芸品として、国内外のファンを魅了し続けています。
特に一本の竹から柄と骨を一体で作る独自の構造は、他地域のうちわにはない堅牢さとしなやかさを両立しています。また、手漉き和紙や布を使った表面仕上げは、透ける光や風の通り方までも計算されており、涼を感じる日本文化の象徴としても評価されています。
近年はデザイン性にも磨きがかかり、伝統技術を活かした現代的なアートうちわとしても人気を集めています。
竹と和紙の調和──素材が生む自然の美
丸亀うちわは、自然素材の魅力を最大限に引き出す工芸品です。骨組みには香川県産の真竹や伊予(愛媛県)の竹が使用され、軽量でありながら強度に優れています。
竹を薄く削いで放射状に広げる工程では、均一な厚みと弾力を生み出すため、職人が手触りと音で微妙な調整を行います。その骨組みに貼られる和紙は、通気性がよく柔らかい光を通すため、使うたびに心地よい涼感を得られます。
紙には越前和紙、阿波和紙、因州和紙、土佐和紙など各地の手漉き和紙が使われ、素材そのものの風合いを活かした仕上げが特徴です。「伊予竹に土佐紙貼りてあわ(阿波)ぐれば讃岐うちわで至極(四国)涼しい」と歌い継がれるように、竹と紙という異素材が調和し、自然の呼吸を感じさせるような心地よさをもたらす点が、丸亀うちわならではの魅力といえるでしょう。
軽さと強度のバランス──使いやすさを支える構造美
丸亀うちわは、驚くほど軽く、それでいて丈夫な点に定評があります。その秘密は、竹の性質を熟知した職人技にあります。竹を割り、火であぶりながら曲げる「曲げ」の工程で形状を安定させ、竹の繊維方向を生かして強度を確保します。
柄と骨を一体で作る「丸柄構造」は、接着や継ぎ目がないため折れにくく、長時間使っても疲れません。また、紙の貼り方や糊の量にも工夫があり、湿気の多い夏でも反りにくく、風を柔らかく送る設計になっています。
構造そのものが意匠であり、無駄のない設計美が光るのも特徴です。使いやすさと美しさを両立した丸亀うちわは、まさに“機能が生むデザイン”の典型といえるでしょう。
涼を演出する日本の美──暮らしを彩る工芸品
丸亀うちわは、単なる実用品にとどまらず、日本の「涼」を象徴する文化的存在です。うちわを仰ぐ所作や音、風の感触には、季節の移ろいを感じる情緒があります。
近年は、和紙の透け感や絵柄の美しさを生かしたインテリアアイテムとしても人気で、壁掛けや店舗装飾、舞台演出などにも用いられています。特に、藍染や金箔を施した高級うちわは、美術工芸として国内外のコレクターから高く評価されています。
さらに、夏祭りや贈答品、ホテルのウェルカムギフトなどにも採用され、伝統工芸が日常に溶け込む好例となっています。丸亀うちわは、涼を感じる道具であると同時に、心を癒やす日本文化の象徴として今も息づいているのです。
丸亀うちわの制作工程と職人技
丸亀うちわは、すべての工程に職人の繊細な手仕事が宿る工芸品です。一本の竹から柄と骨を一体で削り出す独特の製法は、全国のうちわ産地の中でも丸亀だけに受け継がれています。
竹を割り、曲げ、広げ、紙を貼り、乾かし、仕上げる──その工程はおよそ47にも及び、いずれも熟練の経験が求められるものばかりです。量産が難しい分、一つひとつのうちわに微妙な個性と職人の息づかいが宿ります。
ここでは、竹割りから仕上げまで、丸亀うちわづくりを支える代表的な三つの工程を詳しく見ていきます。
竹割りと骨づくり──一本の竹から放射状の美を生む
丸亀うちわの制作は、素材選びと竹割りから始まります。使用するのは香川県産の真竹で、節間が長く、弾力に富んだものが最適とされます。
職人は竹の状態を見極めながら、縦方向に均等な幅で割り、うちわの骨となる部分を作り出します。この「割き」の作業は一見単純に見えますが、力の入れ具合ひとつで仕上がりが大きく変わるため、熟練の技が必要です。
割った竹は、火であぶりながら曲げる「曲げ」工程を経て、放射状に開かれる形へと整えられます。ここで正確な角度と均一な間隔を生み出すことが、美しい骨格と耐久性の両立につながります。一本の竹から、風を操る道具へと姿を変えていく──この工程こそ、丸亀うちわの生命線です。
紙貼りと乾燥──手の感覚で仕上げる一体感
竹骨が完成すると、次に行われるのが和紙や布の貼り付け工程です。使用する紙は通気性に優れた讃岐和紙や美濃紙などで、糊の濃度と気温・湿度のバランスを見ながら職人がその日の“調子”を判断します。
糊を薄く均一に伸ばし、骨の放射線に沿って紙を貼るときの張り具合が仕上がりを左右します。強く貼れば反り、弱ければたるむため、職人は指先の感覚で最適な張力を調整します。
貼り終えたうちわは、湿度管理された室内で自然乾燥させ、紙と竹をしっかり密着させます。この乾燥過程を焦ると歪みが生じるため、一晩から数日をかけて丁寧に乾かします。紙貼りはうちわの“顔”をつくる工程であり、見た目の美しさと風の通り心地を決定づける重要な作業です。
仕上げと装飾技法──実用と美を兼ね備えた最終工程
最後の仕上げでは、うちわの縁を補強し、柄の形を整えます。縁巻きには「へり紙」と呼ばれる細長い紙が使われ、色や素材の組み合わせによって印象が大きく変わります。
次に、持ち手部分を小刀で削り加工する「柄削り」が行われ、手に馴染みやすい形に仕上げられます。装飾が施される場合は、藍染や金箔・銀箔貼りなど多彩な表現が加えられます。
特に高級品では、透かし織の布を表裏両面に貼り合わせた「風布(ふうふ)」があり、素材の透明感が涼感を増し、装飾品としても美しい仕上がりになります。すべての工程を終えた丸亀うちわは、軽さと丈夫さ、そして芸術性を兼ね備えた逸品として完成。使う人の暮らしに寄り添う”風の工芸”として、その命を吹き込まれるのです。
丸亀うちわの産地と地域文化
丸亀うちわは、香川県丸亀市の風土と人々の暮らしに深く根づいた地域工芸です。竹林に恵まれた自然環境と、瀬戸内の穏やかな気候が、うちわづくりに最適な条件を整えてきました。
江戸期から続く職人の技と流通の仕組みは、町全体で支えられ、現在でも地域住民の誇りとして息づいています。丸亀市では伝統工芸を地域産業と観光資源の両面から守る取り組みが進められ、学校教育にも職人体験や竹細工作りが組み込まれるなど、地元文化として次世代への継承が図られています。
うちわは単なる夏の道具ではなく、地域の歴史と人の絆を象徴する“丸亀の顔”なのです。
香川県丸亀市──竹と風が育む“うちわの里”
香川県丸亀市は、うちわづくりに適した立地条件を備えた地域です。「伊予竹に土佐紙貼りてあわ(阿波)ぐれば讃岐うちわで至極(四国)涼しい」と歌い継がれるように、うちわ製作に必要な竹は愛媛県、紙は高知県、糊は徳島県から調達でき、材料がすべて近隣で入手可能という地理的優位性があります。
瀬戸内海に面した温暖な気候は、竹の成長を促し、乾燥や仕上げの工程にも適しています。現在も丸亀市では、年間約1億本を生産、生産量の約9割を占める「うちわの一大産地」としての地位を確立しています。四国という地の利と長年培われた技術の蓄積が、伝統を支え続けているのです。
地域ぐるみの支援体制と職人ネットワーク
丸亀うちわが長く続いてきた背景には、地域全体での支援と協力体制があります。市内では、竹の伐採や材料供給を行う農家、骨組み専門の職人、紙貼りや仕上げを担う加工業者など、分業制が確立されています。
これにより、職人一人ひとりが自らの得意分野に集中でき、品質の高い製品づくりが可能となっています。また、丸亀うちわ協同組合では、技術継承や販路拡大のための展示会・講習会を定期的に開催。
若手育成にも力を入れ、地元高校との連携授業や大学との共同研究も進められています。職人たちは互いを競い合うのではなく、地域の誇りを共有する「技の共同体」として活動しており、この一体感が丸亀うちわの持続的な発展を支えているのです。
「丸亀うちわミュージアム」と観光連携の取り組み

丸亀市では、伝統工芸を観光資源として活用する取り組みも積極的に行われています。その中心的施設が「丸亀うちわミュージアム」です。2023年3月25日に中津万象園内にリニューアルオープンした同館では、江戸時代の古いうちわや道具類の展示に加え、職人による実演や製作体験が行われ、年間を通じて観光客で賑わいます。
特に「自分だけのうちわ作り体験」は人気が高く、伝統工芸士や丸亀うちわニュー・マイスターが丁寧に作り方を教えてくれます。また「うちわ工房『竹』」でも製作体験が可能で、製作から乾燥までの時間を利用して丸亀城内散策も楽しめます。
2023年にはミュージアム移転記念として「丸亀うちわフェスタ2023」が開催され、うちわ製作体験、謎解きクイズラリー、キッチンカーの出店など多彩な内容で地域住民や観光客を楽しませました。こうした活動により、丸亀うちわは地域文化の象徴として、産業振興と観光振興の両立を実現しているのです。
丸亀うちわミュージアム概要
- 住所:〒763-0054 香川県丸亀市中津町25−1
- 電話番号:TEL:0877-24-7055 FAX:0877-43-6966
- 開館時間:9:30~17:00(入館は16:30まで)
- 休館日:毎週水曜日(祝日の場合は翌日)/ 年末年始(12月29日~1月3日)
- 入場料:無料
- 駐車場:乗用車約15台。大型バスの場合は事前に相談ください。
- 公式HP:https://marugameuchiwa.jp/museum
丸亀うちわの現代的価値と海外展開
丸亀うちわは、伝統を守りながらも現代のライフスタイルや国際市場に適応する形で進化を続けています。国内ではインテリアやギフト市場への需要が拡大し、海外では日本文化を象徴するデザインアイテムとして注目を集めています。
近年は、SDGsやエシカル消費の観点から「サステナブルな工芸」としても再評価が進んでおり、竹や和紙という再生可能素材を用いる点が高く評価されています。ここでは、丸亀うちわの現代的価値を支える新しい職人層や、海外展開における動向について紹介します。
伝統とデザインの融合──新世代の職人とブランド戦略
伝統技術を受け継ぎながらも、現代的な感性を取り入れる若手職人の登場が、丸亀うちわに新たな息吹をもたらしています。たとえば、デザインユニットやインテリアブランドとのコラボレーションにより、モダンな色彩やグラフィックを施したうちわが生まれています。
丸亀市内では、女性職人やデザイナー出身の作り手も増え、伝統的な竹割り技法に新しい造形や素材を組み合わせる試みが進行中です。また、「香川うちわブランド認定制度」により、一定の品質基準を満たした商品がブランド化され、海外見本市でも統一的にPRできる仕組みが整っています。
こうした多様な発信力が、丸亀うちわを“進化する伝統工芸”へと押し上げているのです。
環境配慮・サステナブル素材へのシフト
丸亀うちわは、今の時代に即した「持続可能な工芸」としても注目されています。原材料である竹は成長が早く、再生可能な資源であり、環境負荷が少ない点が評価されています。
職人たちは、伐採から加工までを地元で完結させ、輸送エネルギーを抑えた生産体制を築いています。さらに、使用後もうちわを分解・再利用できるよう、接着剤を最小限に抑える工夫も進んでいます。
廃棄されることのない「循環型プロダクト」としての在り方は、海外市場でも高い評価を得ており、エコデザイン賞などへの出品も増えています。サステナブルなものづくりを通じて、丸亀うちわは“地球に優しい伝統工芸”として国際的な存在感を高めています。
国際見本市・ギフト市場で高まる評価
丸亀うちわは、海外のデザイン見本市でも注目を集め始めています。特にフランス・パリの世界最大級国際インテリア見本市「メゾン・エ・オブジェ」では、2024年1月に株式会社紙工芸やまだ(うちわ屋涼)が初出展、2025年1月にも連続出展し、シンプルで機能的な造形と自然素材の質感が評価されています。
また、FUNFAN展を通じて、2007年以降海外22カ国61名のグラフィックデザイナーが参加し、イタリア、台湾、チェコ、アメリカなどで丸亀うちわの展示が行われ、国際的な認知度向上に貢献しています。JICAの草の根技術協力事業では、ラオス国でうちわ産業振興支援プログラムを実施し、技術移転を通じた国際協力も進めています。
加えて、JTBが2022年に「讃岐リミックス」プロジェクトで制作された丸亀うちわの海外販路開拓に乗り出すなど、デジタル販売の拡大により、伝統工芸がグローバル市場と結びつく新たな可能性も見えています。丸亀うちわは今、世界に向けて発信される”風のアート”として新たなステージを迎えているのです。
まとめ
丸亀うちわは、香川県丸亀市が誇る四百年の伝統工芸であり、竹と和紙が織りなす機能美と温もりの象徴です。一本の竹から放射状に広がる骨組みは、熟練職人の技と審美眼の結晶であり、手作業で仕上げられる47もの工程が日本のものづくり精神を体現しています。
近年ではデザイン性や環境配慮の面でも進化を遂げ、国内外の市場で「サステナブルな工芸品」として高い評価を得ています。丸亀の地に吹く穏やかな風とともに受け継がれてきたうちわの文化は、今も新しい形で広がり続け、世界中の人々の暮らしに“涼と美”を届けているのです。