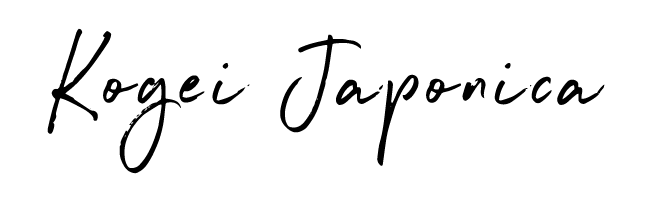小樽雪あかりの路は、北海道・小樽の冬景色の中で、雪と火が生み出す一時的な造形を体感できる代表的な冬のイベントです。街の運河や路地、歴史的建造物の周辺に、雪で作られたオブジェやキャンドルが静かに灯され、昼とはまったく異なる表情の都市空間が立ち上がります。
そこには恒久的な作品ではなく、溶けて消えることを前提とした「儚い造形文化」が存在しています。本記事では、小樽雪あかりの路の成り立ちや特徴を押さえながら、雪と光がつくる造形の魅力を実際に歩いて味わう視点で解説します。
目次
小樽雪あかりの路とは?雪と火でつくられる冬の一時的造形文化
小樽雪あかりの路は、北海道・小樽の冬を代表する市民参加型イベントです。雪でつくられたオブジェや街並みに、ろうそくの柔らかな灯りがともり、街全体が静かな光に包まれます。
派手な演出や大型展示が中心のイベントとは異なり、この催しの魅力は「手作り」と「一時性」にあります。雪と火という身近で儚い素材を使い、冬の短い期間だけ立ち現れる風景は、多くの来場者に穏やかな感動を与えてきました。観光客だけでなく、地域の人々が主役となって作り上げる点も、このイベントならではの特徴です。
イベントの成り立ち:市民の声から始まった冬季観光活性化プロジェクト
小樽雪あかりの路は、最初から大規模な観光イベントとして始まったものではありません。小樽は冬季がオフシーズンとなり観光客がほぼ消えていた状況を改善するため、1997年の小樽観光誘致促進協議会で冬季集客が最優先課題として取り上げられました。
1999年2月に小樽でスキー国体が開催されることから、観光関係者から「冬の観光をアピールする新たなイベント作りが急務」という市民・事業者の声が出ていました。この声を受けて、「寂しい、暗い」というイメージを一新するため、ろうそくの明かりで運河や町を照らし出すことが企画されました。官庁からの押しつけでなく、市民の声から生まれたイベントという点が特徴です。
市民がろうそくを灯すことで街に温もりを取り戻そうとした取り組みが少しずつ広がり、やがて街全体を巻き込むイベントへと成長しました。市民の手仕事が積み重なって現在の形になっている点に、この催しの本質があります。
なぜ「雪」と「ろうそく」なのか──素材選択の意味
このイベントで使われる主な素材は、雪とろうそくです。どちらも特別な道具や技術を必要とせず、誰でも扱える身近な存在です。雪は形を自由につくり替えられ、ろうそくは火を通じて人の気配や温もりを感じさせます。
また、ろうそくの光は電飾とは異なり、揺らぎを伴うため、空間に静かなリズムを生み出します。寒さの中でこそ際立つ小さな光は、見る人の感覚を自然と内側へ向けます。素材の選択そのものが、このイベントの優しさや参加しやすさを形づくっていると言えるでしょう。
恒久的な工芸ではないからこそ生まれる価値
小樽雪あかりの路で生まれる作品は、イベントが終わればすべて姿を消します。雪は溶け、ろうそくの火も消えてしまいます。しかし、その儚さこそがこのイベントの価値です。
恒久的に残る工芸品とは異なり、その瞬間に立ち会うことでしか体験できない風景が、記憶として深く刻まれます。毎年同じ場所で開催されても、同じ景色は二度と現れません。
だからこそ、多くの人が繰り返し訪れ、冬の小樽に足を運びます。一時的な造形だからこそ生まれる特別な体験が、小樽雪あかりの路を長く愛されるイベントにしているのです。
小樽雪あかりの路の開催概要 日程とアクセス方法
小樽雪あかりの路は毎年2月上旬から中旬にかけて開催されます。
- 開催期間:2026年は2月7日(土)から2月14日(土)までの8日間開催予定
- 点灯時間:毎日17時から21時まで
- 入場料:無料
- 場所:小樽運河(北海道小樽市港町)、旧国鉄手宮線、朝里川温泉ほか市内各所
- オフィシャルHP:http://yukiakarinomichi.org/
会場はろうそくの本数が多い順に、運河会場(浅草橋から中央橋区間)、旧国鉄手宮線会場、小樽芸術村会場のほか、天狗山会場や町内会など市内約30か所に設置されます。来場者数は毎年約24万人に達し、北海道を代表する冬の観光イベントとなっています。

電車でのアクセス
札幌からは高速バス「高速おたる号」またはJR函館本線を利用できます。JR小樽駅が最寄り駅で、運河会場までは駅から徒歩5~8分で到着します。開催期間中、一部の高速バスが運河ターミナルまで延長運行されるため、運河会場や手宮線会場へのアクセスがより便利になります。小樽駅の周辺には観光案内所があり、イベントの詳細情報やマップを入手できます。
駐車場と車でのアクセス
小樽雪あかりの路では公式駐車場が用意されていないため、公共交通機関の利用が推奨されています。やむを得ず自動車で訪問する場合は、小樽駅周辺の民間駐車場の利用を検討してください。駐車料金は施設によって異なり、イベント期間中は来場者が集中するため、駐車場の混雑が予想されます。可能な限り公共交通機関の利用をおすすめします。
雪あかりを「工芸」として捉える視点
小樽雪あかりの路は観光イベントとして知られていますが、別の角度から見ると「工芸的な表現」として捉えることもできます。そこには、素材と向き合い、手を動かし、形と光を調整するという、工芸に共通する思考とプロセスが確かに存在します。
雪という自然素材を使い、限られた時間の中で完成させる点は、一般的な工芸品とは異なりますが、手仕事によって空間をつくり出すという本質は共通しています。本章では、雪あかりを工芸的視点から読み解き、造形プロセスや光の設計、そして「消えること」を前提とした表現が持つ意味について整理します。
彫る・削る・灯す:雪造形に共通する手仕事のプロセス
雪あかりの制作には、「彫る」「削る」「灯す」という明確な手仕事の工程があります。雪を積み上げ、不要な部分を削りながら形を整える作業は、木や石を彫刻する工程とよく似ています。
表面をどこまで削るか、厚みをどれくらい残すかによって、完成時の強度や光の透け方が変わります。さらに、内部にろうそくを設置することで、造形は初めて完成します。灯す位置や高さによって、外から見える表情は大きく変化します。
この一連の流れは、偶然に任せた遊びではなく、経験と感覚に基づいた判断の積み重ねです。誰でも参加できる一方で、作り手ごとの工夫や癖が自然と表れ、同じものは二つとして生まれません。こうした工程の積み重ねは、素材は違えど、工芸における手仕事の本質と重なっています。
光と陰影の設計:立体物としての完成度
雪あかりは、昼間に見る造形だけで評価されるものではありません。夜になり、ろうそくの光が入った瞬間に、本来の姿を現します。
雪の厚みや彫りの深さは、光を均一に通す部分と、影を落とす部分を生み出し、立体としての表情を際立たせます。これは偶然ではなく、意識的な「光と陰影の設計」によるものです。薄く削った部分は柔らかく光り、厚みを残した部分は輪郭として影をつくります。
結果として、雪あかりは単なる明かりではなく、光を内包した立体造形として成立します。鑑賞者は、形そのものだけでなく、光がつくる陰影や揺らぎを含めて作品を体験します。この完成度の高さが、雪あかりを一時的な装飾ではなく、造形表現として成立させている要因です。
消失を前提とした表現と、日本の工芸思想との共通性
雪あかりは、イベントが終われば必ず消えてしまいます。この「消失を前提とした表現」は、一見すると工芸とは対極にあるように見えます。しかし日本の工芸思想を振り返ると、そこには共通点が見えてきます。
茶の湯における一期一会や、素材の経年変化を美として受け入れる考え方など、日本の工芸には「永遠でないもの」を尊ぶ感覚が根付いています。雪あかりもまた、その瞬間にしか成立しない美しさを大切にしています。
完成品を所有するのではなく、体験として心に残す点に価値があります。消えてしまうからこそ、人は立ち止まり、光を見つめ、静かに時間を過ごします。この姿勢は、日本の工芸が育んできた美意識と重なり合い、雪あかりを単なるイベント以上の文化的表現へと引き上げているのです。
会場別に見る造形と空間演出
小樽雪あかりの路の魅力は、作品そのものだけでなく、「どこに、どのように置かれるか」という空間演出にもあります。同じ雪あかりでも、会場が変われば見え方や感じ方は大きく異なります。
水辺、線路跡、街なかといった小樽ならではの場所性が、雪と光の表情を引き出しているのです。本章では、代表的な三つの会場に注目し、それぞれの空間特性と雪あかり造形がどのように関係し合っているのかを、一般参加者の視点で分かりやすく紹介します。
小樽運河会場:水辺×雪×光が生む反射と奥行き
小樽運河会場は、雪あかりの路を象徴する風景として多くの人に親しまれています。散策路沿いに並んだ雪のオブジェやアイスキャンドルが運河沿いに設置される一方で、運河の水面にはニシン漁で使われたガラスの浮き玉の中にろうそくを灯した「浮き球キャンドル」が浮かぶことで、その光が水面に映り込み、実際以上の奥行きが生まれます。
雪の白さ、ろうそくの暖色、そして水の反射が重なり合い、視覚的に非常に豊かな空間が形成されます。特に夜になると、光が上下に広がるように感じられ、歩くたびに表情が変化します。
造形自体は比較的シンプルであっても、運河という舞台装置が加わることで、完成度の高い演出になります。写真映えする場所として人気ですが、実際に歩くことで初めて分かる静けさや時間の流れも、この会場ならではの魅力です。
旧国鉄手宮線会場:直線構造と反復配置による造形リズム
旧国鉄手宮線会場は、1880年に北海道で最初に開通した鉄道の跡地を活用した演出が特徴です。かつて線路が通っていた直線的な空間を生かし、ここでは、雪あかりが一定の間隔で反復的に配置され、リズムのある景観がつくり出されます。
直線構造が強調されることで、来場者の視線は自然と奥へと導かれ、歩く行為そのものが鑑賞体験になります。個々の造形は控えめでも、数が集まることで全体として強い印象を残します。
また、線路跡という歴史的背景が、雪あかりの一時性と重なり、過去と現在が静かに交差するような感覚を生み出します。1962年の旅客営業廃止、1985年の路線廃止を経て、約1.6km の散策路として整備されたこの空間は、日本近代化を支えた産業遺産の上で、現代の市民参加型イベントが展開される場となっています。派手さはありませんが、構造的で落ち着いた美しさを味わえる会場です。
街なか会場:日常空間に介入する小さな手仕事

小さな雪あかりが足元を照らし、何気ない道が一時的に特別な場所へと変わります。派手な演出はありませんが、近づいて見ることで手仕事の跡や工夫が感じられ、作り手の存在を身近に感じられます。
住民や店舗が参加することで、街全体がイベントの一部となり、訪れる人も自然とその輪に加わります。街なか会場は、小樽雪あかりの路が「市民のイベント」であることを最も実感できる空間と言えるでしょう。
制作の現場──雪あかりはどのようにつくられているか
小樽雪あかりの路の幻想的な風景は、偶然生まれているわけではありません。その背景には、雪という不安定な素材と向き合いながら、一つひとつ丁寧につくられる制作の現場があります。
見た目はやさしく静かな光景ですが、実際の制作は気象条件や時間との勝負でもあります。本章では、スノーキャンドルの基本的な構造と道具、気温や雪質を読む素材管理の考え方、そして多様な立場の人々が関わる制作体制について紹介し、雪あかりがどのように形づくられているのかを一般参加者の視点で分かりやすく解説します。
スノーキャンドル制作の基本構造と道具
雪あかりの中心的な存在であるスノーキャンドルは、見た目以上に合理的な構造を持っています。基本は、雪を円筒状や立方体状に固め、その内部をくり抜いて空洞をつくり、ろうそくを置くというシンプルな仕組みです。
しかし、この「くり抜き方」や「壁の厚み」によって、光の透け方や強度が大きく変わります。壁が薄すぎると崩れやすく、厚すぎると光が弱くなります。使用する道具も特別なものではなく、スコップやスコップ型の型枠、スプーン、ヘラなど身近なものが中心です。
だからこそ、道具の使い方や力加減に作り手の経験が表れます。完成した形だけでなく、その内部構造まで含めて設計されている点に、雪あかりのものづくりとしての面白さがあります。
気温・雪質・風を読む「素材管理」の考え方
雪あかり制作で欠かせないのが、気温や雪質、風といった自然条件を読む「素材管理」の視点です。気温が高いと雪は溶けやすく、低すぎると固まりにくくなります。また、降りたての雪は軽くて崩れやすく、時間が経った雪は締まりやすいという特性があります。
制作現場では、その日の雪の状態を見極めながら、固める方法や形の大きさを調整します。さらに、風が強い場所では、ろうそくの火が消えやすいため、開口部の向きや深さを工夫します。
これらはマニュアル通りにいかない判断の連続であり、自然素材を扱う工芸や建築とも共通する感覚です。雪あかりは、自然条件を制御するのではなく、読み取り、受け入れながら成立させる表現だと言えるでしょう。
市民・学生・職人経験者が混在する制作体制
小樽雪あかりの路の制作体制の大きな特徴は、多様な背景を持つ人々が同じ現場に立っている点です。地域の市民、地元や近隣の学生、過去に建築や工芸、ものづくりに関わってきた経験者などが、それぞれの立場で参加します。
明確な上下関係や役割分担があるというより、経験の共有や助け合いによって現場が成り立っています。初心者は作りながら学び、経験者は全体を見ながら支えるという循環が自然に生まれています。
この混在した制作体制こそが、雪あかりに多様な表情をもたらす要因です。統一された完成形を目指すのではなく、それぞれの手仕事が集まって一つの風景をつくる。この姿勢が、小樽雪あかりの路を市民参加型イベントとして長く続けてきた原動力となっています。
他の伝統工芸・造形文化との比較
小樽雪あかりの路を「造形文化」として理解するには、他の伝統工芸や冬の造形イベントと比較してみると輪郭がはっきりします。氷彫刻や雪像、灯籠のように「見せる造形」と共通点がある一方、雪とろうそくという素材の選択、市民参加の手仕事、そして消えることを前提とする点で独自の位置を占めます。
ここでは近い文化との違い、工芸的な手触りとの共通性、さらにインスタレーションと工芸の中間領域としての見方を整理します。比較は優劣を決めるためではなく、雪あかりがどの価値を重視しているかを読み解くための道具です。一般参加者の方も、会場で作品を見る視点が増えると体験がより豊かになります。
氷彫刻・雪像・灯籠文化との違い
雪あかりは、氷彫刻や雪像と同じく冬の自然素材を使う造形ですが、目指す方向性が異なります。氷彫刻は透明度と硬さを生かし、輪郭のシャープさや光の屈折を主題にしやすい一方、雪像はボリュームや物語性で「見せる」力が強い表現です。
灯籠文化は火を中心に据え、形は光を包む器として設計されます。雪あかりはその中間にあり、雪の柔らかさが作る曖昧な輪郭と、ろうそくの揺らぎが合わさって初めて完成します。大作を一つ置くより、小さな光を点在させ、街全体の空気を変える設計が核です。
この「分散」と「参加」が、他の冬の造形文化との決定的な違いと言えるでしょう。また、氷彫刻や雪像は完成形の鑑賞が中心になりやすいのに対し、雪あかりは設置後の「火を守る」行為まで含めて作品が維持されます。
風で火が消えれば灯し直し、雪が崩れれば補修する。こうした手入れの反復が、イベント全体を生きた風景にします。灯籠と比べても、雪は透過と崩壊の両方を抱える素材で、厚みの調整や開口部の向きが光の見え方を左右します。結果として、雪あかりは造形物というより、環境と一緒に立ち上がる「場の演出」として体験されるのです。歩く速度で印象が変わる点も特徴です。
木工・石工・漆工に通じる「削る」「整える」感覚
雪あかりの制作は一見すると簡単に見えますが、実際には「削る」「整える」という感覚が重要で、木工や石工、漆工と通じる要素があります。たとえば木工では鉋で面を出し、石工では鑿で形を追い込み、漆工では研ぎで肌を整えます。
雪あかりも同様に、余分を削って厚みを揃え、光が回る面を作ることで完成度が上がります。表面を荒く残せば陰影が強く出て素朴な表情になり、滑らかに整えると光が柔らかく広がります。素材は雪であっても、手の感覚で面と稜線を読み取り、狙った表情に近づけていく点は工芸的です。
さらに道具の当て方も重要で、スコップで形を出し、角やヘラ、スプーンで細部を詰めると壁厚が安定します。雪は削るだけでなく押し固めて密度を上げる工程もあり、制作後に少し置いて雪を締めると崩れにくくなります。
また風上側を厚くする、開口部を深めて火を守るなど、環境条件に合わせた微調整も欠かせません。漆の下地づくりのように、見えない部分の設計が仕上がりを支えます。参加者が補修や点灯を行うことも、仕上げを維持する工程の一部です。作って終わりではなく、手入れまで含めて「作品」を育てる体験になります。
インスタレーションアートと工芸の中間領域としての位置づけ
雪あかりは、現代のインスタレーションアートにも近い側面を持ちます。作品は単体で完結するのではなく、運河や線路跡、街路といった場所と結び付くことで意味を獲得し、鑑賞者の移動や滞在時間によって体験が変化します。一方で、制作の中心が市民の手仕事であり、形をつくる工程に素材理解と技術が必要な点は工芸的です。
つまり雪あかりは、アートの「場の設計」と工芸の「手の技」を同時に含む中間領域に位置します。工芸品が長期保存を前提に仕上げや管理を行うのに対し、雪あかりは消えることを受け入れ、その短さが集中を生みます。
だからこそ配置計画や導線が重要になり、夜の光景を一つの環境作品として成立させます。さらに評価軸も中間で、火が安定して灯るか、歩行の安全が確保されているかといった配慮も作品の一部になります。
参加者が補修や点灯を続けることで風景が維持され、来場者は完成品というより、立ち上がり続ける場に居合わせます。所有できないからこそ光景が記憶に残り、また訪れる動機になる。この循環が、雪あかりを地域文化として定着させています。工芸とアートの境界をやさしく越える入口としても魅力です。
工芸・ものづくり好きにとっての小樽雪あかりの路の価値
小樽雪あかりの路は、完成度の高い造形を鑑賞するイベントであると同時に、ものづくりの考え方そのものを体験できる場でもあります。雪という扱いの難しい素材を前に、試し、調整し、手を入れ続ける姿勢は、多くの工芸や手仕事と共通しています。
以下では、小樽雪あかりの路が持つ独自の価値を、プロセス、素材、経験という三つの切り口で整理します。完成品を所有する喜びとは異なる、体験としての豊かさが、このイベントにはあります。
完成品よりプロセスを味わうイベントであること
小樽雪あかりの路の大きな特徴は、完成した造形以上に、その背後にある制作プロセスが感じ取れる点にあります。雪あかりは、一度つくって終わりではなく、気温や風の変化に応じて手を入れ直し、火を守り続けることで成立します。
これは、削りや研ぎを繰り返しながら仕上げていく工芸の工程とよく似ています。会場を歩くと、わずかな補修の跡や、光を調整した痕跡が目に入り、作り手の判断の積み重ねが自然と伝わってきます。
完成品だけを鑑賞する展示では見えにくい「途中の思考」が可視化されている点は、ものづくり好きにとって大きな魅力です。結果よりも過程に価値を見いだす姿勢が、このイベント全体を貫いています。
地域素材を使った表現の可能性を考える場
雪あかりの路は、地域にある素材をそのまま使って表現を行う実践の場でもあります。雪は小樽の冬にとって避けられない存在であり、特別に用意された材料ではありません。
その身近な素材を、造形や光の工夫によって価値ある風景へと変えている点は、地域工芸やローカルなものづくりを考える上で示唆に富んでいます。高価な素材や高度な設備がなくても、環境を読み、手を動かすことで表現は成立する。
その事実は、木や土、石といった地域素材を扱う工芸とも深く通じています。雪あかりは、土地の条件を制約ではなく可能性として捉える視点を、来場者に静かに提示してくれます。
恒久作品とは異なる「経験としての工芸」
工芸品は、完成後も長く使われ、保存されることが前提となる場合が多いですが、雪あかりは必ず消えてしまいます。しかし、その一時性こそが、体験としての価値を高めています。
現地で歩き、立ち止まり、光の変化を感じる時間そのものが「作品」となり、記憶として残ります。これは、所有する工芸とは異なる、「経験する工芸」とも言える在り方です。作り手も鑑賞者も同じ時間と環境を共有し、その場に立ち会うことで価値が生まれます。
ものづくりを形だけでなく、時間や行為を含めて捉えたい人にとって、小樽雪あかりの路は、工芸の可能性を広げてくれる貴重な場と言えるでしょう。
まとめ
小樽雪あかりの路は、雪とろうそくという身近で儚い素材を使い、市民の手仕事によってつくられる冬のイベントです。完成された作品をただ鑑賞するのではなく、彫り、削り、灯し、守るというプロセスそのものが風景に表れています。
会場ごとに異なる空間演出や、自然条件と向き合う制作の工夫は、工芸やものづくりの考え方とも深く通じています。恒久的に残らないからこそ、その場に立ち会う体験が強く記憶に残り、毎年違う表情を見せてくれます。
観光としても、ものづくり文化としても楽しめる小樽雪あかりの路は、冬の小樽を静かに味わうための特別な時間を提供してくれるイベントです。